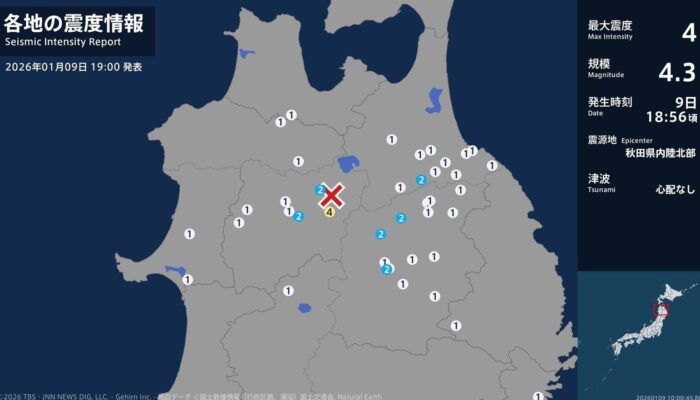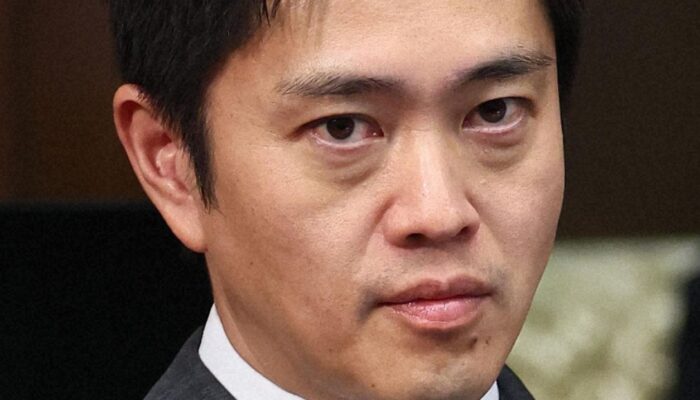「診療報酬2.22%増」の美名に隠された国民負担増の真実
政府・与党が来年度の診療報酬改定において、全体で2.22%の引き上げを決定したとの報道がなされた。医療従事者の賃上げを実現し、物価高騰に対応するため、というのがその理由だ。一見すると、医療現場を支える方々の待遇改善につながる、喜ばしいニュースのように聞こえるかもしれない。
しかし、我々はこの決定の裏側にあるものを冷静に見つめ、その本質を問わなければならない。この決定は、果たして本当に日本の将来、すなわち国益にかなうものなのだろうか。保守的な観点から言えば、答えは断じて「否」である。
財源は誰が払うのか? 見過ごされる国民負担の現実
まず、最も根本的な問題を指摘せねばならない。診療報酬の財源は、天から降ってくるわけではない。我々国民が汗水流して稼いだ収入から天引きされる健康保険料と、納めた税金によって賄われている。
つまり、診療報酬の「引き上げ」は、そのまま「国民負担の増大」に直結するのである。「医療従事者の賃上げ」という耳障りの良い言葉の裏で、現役世代の可処分所得はさらに減少し、企業の経営は圧迫される。この厳しい現実から目を背けてはならない。
我が国は、少子高齢化という構造的な課題に直面し、社会保障費は自然増だけでも国家財政を蝕んでいる。このような状況下で、さらなる公定価格の引き上げに踏み切ることは、財政規律を著しく軽視した判断と言わざるを得ない。財務省が引き下げを主張したのは、国家財政の持続可能性を考えれば至極当然のことであった。
聖域化する医療費―改革なき引き上げの愚
今回の改定では、薬の公定価格である「薬価」は引き下げられた。市場の実勢価格を反映させるこの動き自体は評価できる。しかし、問題は医師の技術料や人件費にあたる「本体」部分が大幅に引き上げられたことだ。
なぜ、医療界だけがこのような「聖域」として扱われるのか。一般の民間企業は、物価高や人件費増を乗り越えるため、血の滲むような効率化や生産性向上の努力を続けている。医療界において、そうした自助努力は十分になされているのだろうか。
安易に公定価格の引き上げに頼る構造は、医療機関の経営努力を削ぎ、非効率な経営を温存させることにつながりかねない。診療報酬を引き上げる前に、後発医薬品の使用促進の徹底、IT化による業務効率の改善、そして何より、過剰な診療や投薬を抑制する仕組みの構築など、やるべき改革が山積しているはずだ。
今回の決定の背景には、強大な政治力を持つ日本医師会など、業界団体の存在がちらつく。政治家が、国家の将来よりも目先の選挙や業界の歓心を買うことを優先した結果であるとすれば、それは国民に対する背信行為に他ならない。
将来世代への責任を放棄するのか
そして何より深刻なのは、この負担増が、我々の子供や孫、まだ生まれぬ将来世代に重くのしかかるという事実である。
現在の社会保障制度は、現役世代が高齢者を支える構造になっている。しかし、少子化が進む中で、この仕組みがもはや持続不可能であることは誰の目にも明らかだ。今回の安易な診療報酬引き上げは、問題の先送りに他ならず、将来世代への「ツケの先送り」でしかない。
世界に誇るべき国民皆保険制度を守るためと称しながら、その制度を破綻に導くような決定を下すことは、本末転倒である。真にこの制度を守りたいのであれば、軽微な症状での受診に対する自己負担の引き上げ(応益負担の導入)や、保険適用範囲の見直しなど、痛みを伴う聖域なき改革にこそ着手すべきなのである。
我々国民は、社会保障の「受益者」であると同時に、重い「負担者」であることを再認識する必要がある。そして政治には、業界団体の顔色をうかがうのではなく、国家百年の計に立ち、将来世代への責任を果たす、真に保守的な判断を強く求めるものである。
————-
ソース