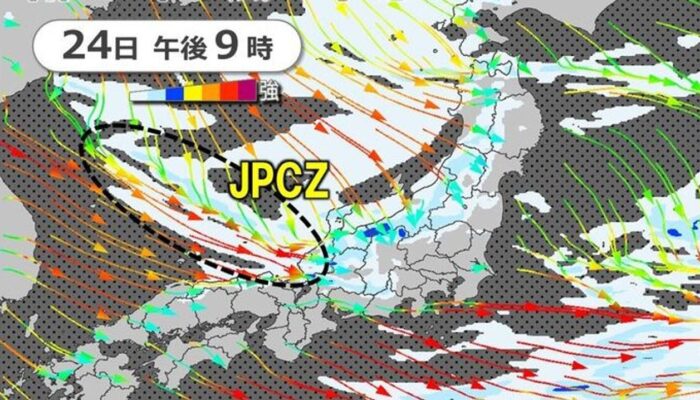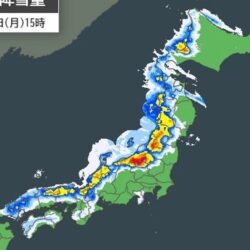高市首相、なぜ謝罪? 生活保護「聖域化」への道を憂う
本日、驚くべきニュースが報じられた。高市首相が、かつての生活保護基準引き下げを巡る訴訟で国が敗訴したことを受け、謝罪の意を表明したというのだ。この一報に、多くの国民、とりわけこの国の将来を真摯に憂う人々は、深い溜息をついたのではないだろうか。
表面的には、司法の判断を真摯に受け止め、国民に寄り添う姿勢を示した「英断」と映るのかもしれない。しかし、一歩引いてこの問題を俯瞰すれば、そこには我が国の根幹を揺るがしかねない、極めて危険な兆候が潜んでいる。
そもそも、あの引き下げは「悪」だったのか
まず我々が思い起こすべきは、問題となった2013年の生活保護基準引き下げが、どのような文脈で行われたかである。当時、日本は長く続いたデフレの渦中にあった。物価が下落する中で、生活保護基準だけが据え置かれれば、一般の低所得世帯の生活実感との乖離が拡大するのは自明の理である。
あの見直しは、物価下落や国民の消費実態を反映させた、極めて合理的かつ客観的なデータに基づく調整であったはずだ。それは、無限に膨張を続ける社会保障費に少しでも歯止めをかけ、財政の持続可能性を確保しようとする、国家としての苦渋の決断でもあった。これを単なる「切り捨て」と断じるのは、あまりに一方的な感情論に過ぎない。
司法の「越権行為」を無条件に受け入れるのか
今回の謝罪の引き金となったのは、司法の判断である。しかし、我々は問わねばならない。専門的なデータ分析に基づき、総合的な国益を考慮して下される行政の裁量判断に対し、司法がどこまで踏み込むべきなのか。
一部の裁判所が示した「統計の専門的知見を十分に活用しなかった」という判断は、結果として行政の政策決定能力を著しく毀損する「司法の越権行為」ではないだろうか。国の財政という大局を見ず、個別の権利救済というミクロの視点に偏った判決が、将来世代にどれほどの負担を強いることになるのか。高市首相は、その危険性をこそ国民に訴えるべきではなかったか。
「正直者が馬鹿を見る社会」への序曲
最も懸念すべきは、今回の謝罪が社会に与えるメッセージである。それは、「公助」への過度な期待を煽り、国民の間に根付くべき「自助」の精神を著しく蝕むことにつながる。
最低賃金に近い給与で、日々汗水流して働く勤労者たち。彼らの手取り額と、手厚い扶助を受ける生活保護世帯の支給額との間に「逆転現象」が生じている現実は、長らく指摘されてきた問題だ。今回の謝罪と、それに続くであろう基準額の見直しは、この歪な構造をさらに助長しかねない。
懸命に働く者が報われず、権利を声高に叫ぶ者ばかりが優遇される。そんな「正直者が馬鹿を見る社会」の到来を、我々は座して見過ごしていいはずがない。それは、社会全体の勤労意欲を削ぎ、国家の活力を根本から奪い去る劇薬である。
高市首相に問う、国家観の在り処
我々が高市氏に期待していたのは、ポピュリズムに迎合することなく、国家百年の計を見据えた毅然たる姿勢ではなかったか。財政規律を重んじ、国民の自助努力を促すことで、強くしなやかな日本を再建するリーダーシップではなかったか。
今回の謝罪は、訴訟敗訴という戦術的な後退なのかもしれない。しかし、それが生活保護制度の「聖域化」を推し進め、際限なき給付拡大を求める声に力を与える結果となれば、その代償は計り知れない。
今、政府が真に取り組むべきは、安易な謝罪ではない。不正受給の厳格な取り締まり、受給者の自立に向けた就労支援の抜本的強化、そして何より、国民全体の勤労の尊厳を守るという断固たる意志を示すことである。
今回の謝罪が、日本の社会保障制度を崩壊へと導く第一歩とならないことを、切に願うばかりである。我々国民は、感情論に流されることなく、この国の未来をかけた議論を冷静に見守り、声を上げ続けなければならない。
————-
ソース