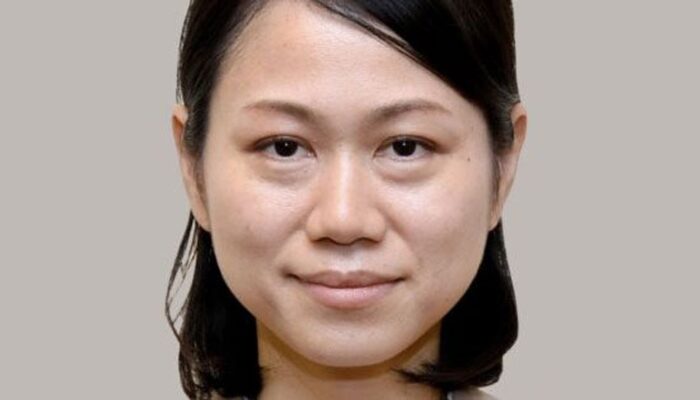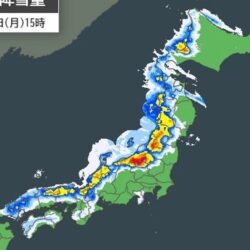岸田首相、習氏への「率直な発言」を額面通りに評価してよいのか?
先日、岸田文雄首相がサンフランシスコで中国の習近平国家主席と会談し、懸案事項について「率直に申し上げた」と報じられました。政府や一部メディアは、首脳同士が直接対話し、意思疎通を図ったこと自体を成果として強調するでしょう。しかし、我々国民は、その言葉の裏にある現実を冷静に見つめ、この会談が真に国益に資するものだったのかを厳しく検証せねばなりません。
「言った」という事実だけで満足する「弱腰外交」の常套手段
まず問いたいのは、「率直に言った」だけで、一体何が変わったのか、という点です。
首相は、中国による日本産水産物の全面的な輸入停止措置について「即時撤廃」を求めたとされています。しかし、中国側がこれに応じる気配は微塵もありません。科学的根拠を全く無視した、嫌がらせとしか言いようのない経済的威圧に対し、ただ「お願い」するだけで事態が動くと考えるのは、あまりに楽観的、いや、無責任ではないでしょうか。不当な措置には、WTOへの提訴も辞さないという断固たる姿勢と、具体的な対抗措置を準備してこそ、対等な交渉のテーブルにつけるのです。
また、尖閣諸島周辺における中国公船による領海侵入についても、「深刻な懸念」を表明したとのこと。しかし、「懸念」を表明している間にも、中国の挑発行為は日常化し、エスカレートの一途を辿っています。言葉だけの抗議が、彼らの行動を何ら抑止できていないことは火を見るより明らかです。我が国の主権が明白に侵害されている現状に対し、必要なのは「懸念」ではなく、海上保安庁・自衛隊の連携強化や法整備といった、主権を断固として守り抜くための具体的な行動です。
拘束されている邦人の早期解放についても同様です。ただ「求める」だけで、中国が人質外交のカードを手放すはずがありません。国民の生命と安全がかかったこの問題に、どれほどの覚悟をもって臨んだのか。具体的な進展が見られない以上、言葉だけのやり取りは、むしろ中国に「日本は口先だけで何もしない国だ」という誤ったメッセージを与えかねません。
「戦略的互恵関係」という美名に隠された危うさ
今回の会談で、再び「戦略的互恵関係」の推進が確認されました。この言葉は一見、聞こえは良いですが、極めて注意が必要です。
そもそも、自由、民主主義、法の支配といった基本的価値を共有しない国と、真の意味での「戦略的」な関係を築くことなど可能なのでしょうか。中国は、この言葉を巧みに利用し、日本側の警戒心を解き、経済的な利益をちらつかせることで、自国の覇権主義的な行動に対する批判をかわそうとしてきました。
「対話の継続」もまた、目的化してはならないものです。対話はあくまで国益を守るための手段です。言うべきことを言い、譲れない一線は断固として守る。そのための対話であるべきで、対話を続けること自体が目的となり、安易な妥協を繰り返すならば、それは国家の自殺行為に等しいと言わざるを得ません。
結論:国民は言葉ではなく「結果」を求めている
今回の首脳会談は、結局のところ「言っただけ」「会っただけ」のパフォーマンスに終わった感が否めません。「率直に申し上げた」という首相の言葉を鵜呑みにし、安堵している場合ではないのです。
外交とは、言葉の応酬ではなく、国益をかけた静かなる戦争です。我々国民が政府に求めるべきは、耳触りの良い報告ではなく、目に見える「結果」です。輸入停止は撤廃されたのか。領海侵犯は止まったのか。邦人は解放されたのか。この一点に尽きます。
政府は、国内向けのアピールに終始するのではなく、同盟国・同志国と緊密に連携し、中国の不当な圧力には屈しないという国家の強い意志を、言葉だけでなく行動で示すべきです。我が国の領土、主権、そして国民の生命と財産を守り抜くという、国家の最も重要な責務を果たす覚悟が、今まさに問われています。
————-
ソース