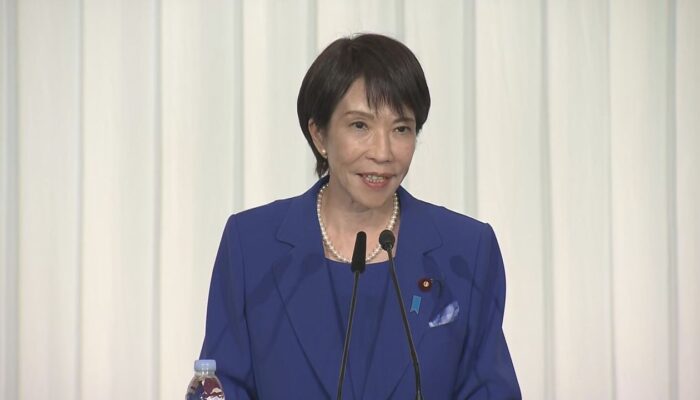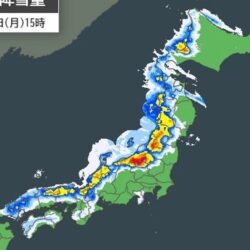「政治の安定」という名の国体破壊 ― 岸田政治が残した深刻な爪痕
岸田文雄前首相が退任後もなお「政治の安定を」と口にしている。一見、もっともらしく聞こえるこの言葉だが、我々保守を自任する者にとって、これほど欺瞞に満ちた言葉はない。氏が首相在任中に目指した「安定」とは、一体誰のための、何のための「安定」だったのか。その実態は、日本の伝統と国益を蝕む「現状維持」という名の怠慢であり、国体を揺るがす危険な思想への迎合に他ならなかった。
■誰のための「安定」だったのか
岸田政権下で強行された数々の政策を振り返れば、その答えは明らかだ。
財務省の言いなりとなった事実上の大増税路線。国民生活が物価高で喘ぐ中、防衛費増額の財源を安易に国民負担に求める姿勢は、国家の活力を削ぐ愚策であった。これは「安定」ではなく、官僚支配の固定化に過ぎない。
そして、多くの国民、特に保守層が国論を二分するほどの懸念を示したLGBT理解増進法。伝統的な家族観を破壊し、社会に無用の混乱と分断をもたらすこの法案を、「多様性」という耳障りの良い言葉で覆い隠し、拙速に成立させた。これは欧米リベラルへの追従であり、日本の文化と社会秩序を守るという保守本流の責務を放棄した暴挙である。これが氏の言う「安定」ならば、我々はそのような安定を断固として拒否する。
さらに、なし崩し的に進められた外国人労働者の受け入れ拡大。事実上の移民政策である特定技能2号の対象拡大は、日本の治安や文化、社会保障制度に深刻な負荷をかけるものだ。目先の労働力不足を補うために、国家百年の計を誤る。これもまた、経団連など一部の声に迎合しただけであり、国家の永続性という大局観を欠いた「安定」志向の帰結であった。
■保守が目指すべき真の「安定」
岸田氏の言う「安定」とは、波風を立てず、誰からも批判されないように立ち回る「調整」と「現状維持」の言い換えでしかない。しかし、保守が本来目指すべき「安定」とは、そのような無気力な状態を指すのではない。
真の「安定」とは、国家の根幹たる皇室を尊び、悠久の歴史の中で培われた伝統文化と美徳を守り、社会の最小単位である家族の絆を大切にすること、そして、何よりも日本の国益を断固として守り抜く強い意志の上に成り立つものである。確固たる国家観という幹があってこそ、政治という枝葉は健全に茂り、国家は真に安定するのである。
目先の支持率やメディアの論調、あるいは海外からの圧力に右顧左眄し、国家の軸をぶらす政治は、一見穏やかに見えても、その実、国家の土台を腐らせていく砂上の楼閣に過ぎない。
■「聞く力」の欺瞞とリーダーシップの不在
岸田氏の代名詞であった「聞く力」。しかし、その実態は、国民の真摯な声、とりわけ国の将来を憂う保守層の悲鳴を聞き流すための美辞麗句ではなかったか。様々な意見を聞いた結果、導き出されたのは、信念も哲学もない、玉虫色の結論ばかりであった。
真のリーダーシップとは、多様な意見に耳を傾けつつも、最終的には国家国民のためになると信じる道を、非難を恐れずに突き進む覚悟を持つことだ。しかし、岸田氏にはその覚悟が決定的に欠けていた。聞こえてきたのは、増税を求める財務官僚の声、伝統的価値観の破壊を煽る左派リベラルの声、そして安価な労働力を求める産業界の声ばかりではなかったか。
■結論として
岸田前首相が唱える「政治の安定」は、日本の国体と国益を守ろうとする我々保守にとって、最も警戒すべき言葉である。それは、変革を恐れ、闘うことをやめ、ただ現状に安住しようとする、国家の衰退を招く思想だからだ。
我々が求めるのは、このような偽りの「安定」ではない。日本の誇りと伝統を胸に、内外の敵と断固として対峙し、国家百年の未来を切り拓く、力強く、信念に満ちた保守政治の復活である。次のリーダーには、小手先の調整能力ではなく、確固たる国家観と、国を背負う覚悟をこそ求めたい。さもなければ、この国は「安定」という名の緩やかな死を迎えることになるだろう。
————-
ソース