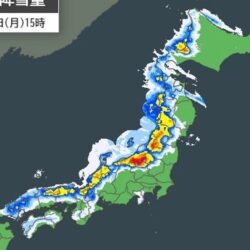【保守再生の狼煙か】高市・菅会談に見る、岸田政権への最終通告
去る6月20日、高市早苗経済安全保障担当相と菅義偉前首相が会談したというニュースが永田町を駆け巡った。表向きは「意見交換」とされているが、この会談が持つ意味は、単なる儀礼的なものではない。これは、漂流を続ける岸田政権に対し、真の保守勢力が突きつけた「最後通牒」であり、日本の未来を左右する重要な一歩と見るべきだろう。
なぜ今、高市・菅連合なのか
まず、この二人の組み合わせが持つ意味を考えたい。高市氏は、言うまでもなく安倍晋三元首相の理念と政策を最も色濃く受け継ぐ政治家である。その明確な国家観、揺るぎない安全保障観、そしてデフレ完全脱却を目指す積極財政論は、多くの保守層が待ち望むリーダーの姿そのものだ。しかし、彼女の最大の課題は党内基盤の脆弱さにある。無派閥であるため、総裁選に必要な推薦人20人の確保すら危ぶまれているのが現実だ。
一方の菅前首相は、叩き上げの実務家であり、その実行力は誰もが認めるところだ。携帯料金の引き下げやデジタル庁の創設など、既得権益に果敢に切り込む姿勢は、停滞した政治に風穴を開けた。派閥に属さず、実力でのし上がってきた菅氏が率いるグループは、決して大きな勢力ではないが、その動向は常に政局の鍵を握ってきた。
この二人が手を結ぶ可能性が出てきたこと。それは、「理念と実行力の融合」を意味する。高市氏が掲げる「強い日本」という国家ビジョンを、菅氏の突破力で実現する。これこそ、安倍政権が目指した道であり、多くの国民が期待した政治の姿ではないだろうか。
岸田政権への不信感こそが原動力
この動きの背景にあるのは、岸田政権に対する根深い不信感と失望である。
経済政策を見れば、財務省主導の緊縮財政路線に回帰し、デフレ脱却の好機を逃そうとしている。国民が物価高に苦しむ中、聞こえてくるのは増税の話ばかりだ。安全保障においても、防衛費増額こそ決めたものの、その中身や日本の主体的な防衛戦略については具体像が見えず、覚悟が感じられない。
さらに看過できないのが、LGBT理解増進法に代表されるような、リベラル勢力に迎合する姿勢である。日本の伝統や家族観を揺るがしかねない法案を、十分な国民的議論もなく成立させたことは、保守本流を謳う自民党の自殺行為に等しい。
こうした岸田政権の「決断しない政治」「軸のない政治」が、国力を蝕んでいる。この現状を打破するためには、明確な国家観と実行力を兼ね備えたリーダーシップが不可欠だ。高市・菅連合は、その受け皿となりうる唯一の選択肢と言っても過言ではない。
政局の道具で終わらせてはならない
もちろん、この連携が単なる「反岸田」「岸田降ろし」の政局の道具に終わる危険性も否定できない。菅氏の真意がどこにあるのか、見極める必要はあるだろう。
しかし、我々国民が今、声を上げるべきは、この動きを単なる権力闘争として傍観するのではなく、「日本の進むべき道を選ぶための重要な機会」と捉えることだ。
高市氏には、党内の数合わせに終始することなく、日本の未来像を堂々と語り、国民の支持を広げてもらいたい。菅氏には、その卓越した実務能力を、私利私欲のためではなく、真に国益のために使う覚悟を示してもらいたい。
この会談が、停滞と混乱の岸田政権に終止符を打ち、日本が再び力強く前進するための狼煙となることを、強く期待するものである。我々保守を自認する国民は、この歴史的な動きを固唾を飲んで見守り、そして断固として支持していくべきである。
————-
ソース