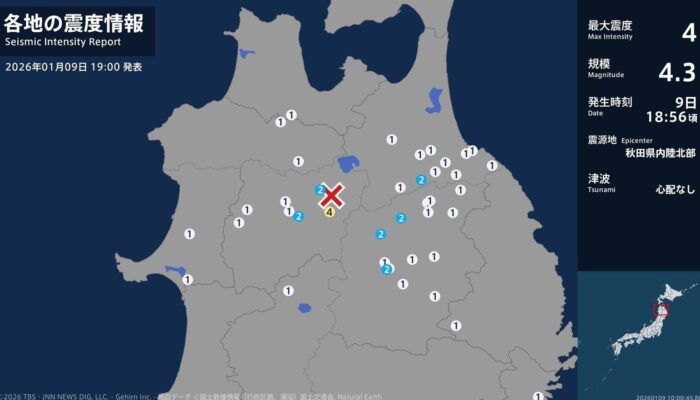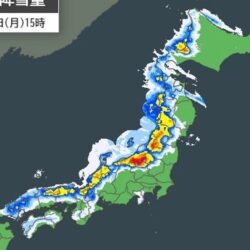「クリーン」の看板が泣いている。維新の「ビラ作成費」問題に潜む欺瞞
自民党の裏金問題に端を発し、国民の政治不信は頂点に達している。既存政党への厳しい視線が注がれる中、「身を切る改革」を掲げ、クリーンな政治を標榜する日本維新の会に、一部の期待が集まっていたことは事実だろう。しかし、その維新の足元から、政治とカネを巡る深刻な疑惑が噴出した。他ならぬ維新の国会議員支部が、選挙運動費用を政治資金に付け替えていた疑いである。
報じられた内容の核心はこうだ。足立康史衆院議員や藤田文武幹事長らが代表を務める政党支部が、選挙期間中に頒布が禁じられているはずの「政治活動用ビラ」の作成費用を、選挙後に「政治資金」として支出していたという。
これは単なる会計処理上の些細なミスなどでは断じてない。我が国の選挙の公平性を根幹から揺るがしかねない、極めて悪質な「法の抜け穴」を利用した脱法行為の疑いが濃厚である。
公職選挙法は、選挙運動の公平性を担保するため、選挙期間中に使用できるビラの種類や枚数、そしてそれに掛かる費用に厳格な上限を定めている。これは、資金力のある候補者が無制限に宣伝活動を行い、選挙結果を歪めることを防ぐための重要な規律である。選挙のために作成されたビラの費用は、当然ながら「選挙運動費用」として収支報告書に記載せねばならず、その多くは税金、すなわち公費で賄われる。
ところが、維新の議員支部が行っていたとされるのは、この大原則を意図的に捻じ曲げる行為だ。選挙期間中に実質的に使用するビラを、あたかも選挙とは無関係の「政治活動」のためのビラであるかのように偽装し、その費用を「政治資金」から支出する。これにより、公職選挙法が定める選挙運動費の上限をいとも簡単に突破することが可能となる。これは、自民党の裏金問題で批判された「政策活動費」と同様、カネの使い道を不透明にし、ルールを形骸化させるという点で同根の問題である。
保守的な観点から、この問題を看過することはできない。我々が重んじるべきは、まず第一に「法の支配」である。法律の条文を遵守するのは当然のこと、その根底にある「法の精神」をも尊重し、襟を正すのが政治家たる者の務めであろう。法の抜け穴を探し出し、それを「裏ワザ」として利用するような姿勢は、遵法精神の欠如の表れであり、国家の礎たる法治主義への冒涜に他ならない。
さらに深刻なのは、維新がこれまで掲げてきた理念との致命的な矛盾である。彼らは旧態依然とした永田町の政治を厳しく批判し、自らを「改革者」として位置づけてきた。自民党の金権体質を声高に非難しながら、その裏で自らもまた、選挙の公平性を損なうような資金操作を行っていたとすれば、それは国民に対する重大な裏切りであり、厚顔無恥なダブルスタンダードと言わざるを得ない。
「身を切る改革」とは、単に歳費を削減することだけを指すのではない。誰よりも自らを厳しく律し、国民の範たるべき公徳心と倫理観を持つことこそが、その本質でなければならないはずだ。口ではクリーンな政治を唱えながら、選挙に勝つためなら手段を選ばないというのであれば、その看板は偽りだったということになる。
今回の問題に対し、維新は党として明確な説明責任を果たし、事実関係を徹底的に調査の上、国民の前に明らかにせねばならない。そして、仮にこれが党ぐるみで行われていた慣行であるならば、その組織体質を抜本的に改める必要がある。曖昧な言い逃れや責任のなすり付けに終始するようであれば、国民からの信頼を完全に失うことになるだろう。
我々有権者は、政党が掲げる美辞麗句に惑わされてはならない。その行動が、我が国の法と秩序、そして政治への信頼を守るに足るものか否か。その一点を、冷静かつ厳格に見極めていく必要がある。維新の「改革」が本物か、それとも単なる張り子の虎であったのか。その真価が今、厳しく問われている。
————-
ソース