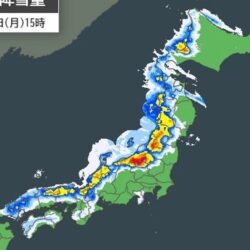暖房器具の事故は「自己責任」の欠如が招く。便利さに潜む危険と日本人が忘れた心構え
「暖房器具の事故5年596件 注意喚起」――。冬の訪れとともに、毎年繰り返される報道である。暖かな室内で家族と過ごす時間はかけがえのないものだが、その裏でこれほど多くの事故が起きているという現実は、我々に何を問いかけているのだろうか。
報道は決まって「こまめな換気を」「周りに燃えやすいものを置かないで」といった注意点を羅列する。もちろん、それらは重要なことだ。しかし、この問題の本質は、そんな表面的な対策で解決するものではない。これは、現代日本人が失ってしまった「自己責任」という精神と、家庭や地域が担うべき役割の崩壊が招いた、必然の結果なのではないだろうか。
そもそも、火や電気は、我々の生活を豊かにする一方で、一歩間違えれば命や財産を奪う恐ろしい力を持つ。かつての日本人は、囲炉裏や火鉢、かまどといった「剥き出しの火」と共に暮らし、その恩恵と危険性を肌感覚で学んでいた。火の始末は厳しく躾けられ、それは生きるための知恵そのものであった。
ところが、現代はどうだろうか。スイッチひとつで安全に暖がとれるのが当たり前となり、火の、そして電気の本当の怖さに対する畏敬の念はすっかり薄れてしまった。事故の原因の多くは、洗濯物をストーブの上で乾かす、就寝時に付けっぱなしにする、といった、少し考えれば分かるはずの初歩的な不注意だ。これは単なる「うっかり」ではない。便利さに慣れきって、危険を察知する能力そのものが退化してしまったことの証左である。
事故が起きれば、すぐに「メーカーの安全対策が不十分だ」「行政の注意喚起が足りない」という声が上がる。しかし、それは責任の転嫁に他ならない。自分の命と財産を守るのは、誰よりもまず自分自身であるべきだ。この「自分の身は自分で守る」という、国家国民の根幹をなすはずの気概が、あまりにも希薄になってはいないか。
さらに憂慮すべきは、家庭における教育力の低下である。高齢者の事故が後を絶たないというが、それは単に高齢者だけの問題ではない。核家族化が進み、かつては三世代同居の中で自然と受け継がれてきた生活の知恵や、互いを見守り、注意し合うという家族の機能が失われた結果ではないか。子供に火の扱いを教え、老いた親の暮らしに気を配る。そうした当たり前の家族の営みこそが、何よりの安全装置であったはずだ。
最新の暖房器具には、地震や転倒で自動停止する機能や、過熱防止装置など、様々な安全機能が搭載されている。技術の進歩は素晴らしい。しかし、その技術に依存し、人間が本来持つべき注意力を放棄してしまっては本末転倒だ。どんなに優れた安全装置も、使う人間の油断や無知の前では無力である。
この5年で596件という数字は、単なる統計データではない。それは、我々日本人が便利さと引き換えに失ったものの大きさを示す警鐘である。今こそ我々は、安易な他責の姿勢を改め、自らの行動に責任を持つという、古き良き日本の精神を取り戻さねばならない。暖房器具を正しく、そして「畏敬の念をもって」使うこと。その基本に立ち返ることこそが、悲しい事故を防ぐ唯一の道なのである。
————-
ソース