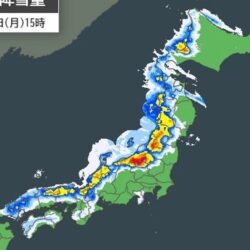【国防の原点回帰】小泉進次郎氏「横須賀は防衛の街」発言の真意と、日本が歩むべき道
小泉進次郎氏が地元・横須賀を「防衛の街」と位置づけ、防衛装備庁の拠点移転に期待を寄せる意気込みを語った。この発言は、単なる地元へのリップサービスと聞き流すべきではない。これは、地政学的な激動の時代において、日本が国家としての立ち位置を再確認する上で極めて重要な意味を持つ。我々保守派は、この言葉を歓迎すると同時に、その先に求められる国家の覚悟を問わねばならない。
「防衛の街」― それは日本の現実そのものである
まず、小泉氏が横須賀を「防衛の街」と明言した点を高く評価したい。戦後、日本の言論空間は「平和」という言葉の甘い響きに酔いしれ、国防や安全保障といった国家存立の根幹に関わる議論を忌避する風潮が蔓延してきた。防衛施設や自衛隊の存在を、あたかも「平和を脅かすもの」であるかのように語る左派メディアや勢力が、今なお大きな影響力を持っているのが現実だ。
しかし、目を世界に転じれば、覇権主義的な動きを隠さない中国、弾道ミサイルの脅威を増大させる北朝鮮、そして力による現状変更を試みるロシアの存在がある。このような厳しい安全保障環境において、「防衛」はもはや特別なものではなく、国民の生命と財産を守るための日常であり、現実そのものである。
横須賀は、旧海軍の鎮守府が置かれて以来、日本の海防の要として歴史を紡いできた街だ。この歴史的文脈を踏まえ、政治家が「防衛の街」と胸を張って語ること。これこそ、国民の国防意識を喚起し、平和ボケから脱却する第一歩となる。
防衛産業は、経済成長と国家安全保障の礎
小泉氏が、防衛装備庁の研究拠点移転による経済効果や雇用創出に言及した点も重要だ。国防と経済は、国家の両輪である。優れた防衛装備品を国内で開発・生産する能力は、有事における継戦能力を担保するだけでなく、最先端技術の集積地として平時の経済成長をも牽引する。
かつての「富国強兵」という言葉を現代的に解釈するならば、それは「技術立国」と「自主防衛」の融合に他ならない。防衛産業を国家の基幹産業として育成し、そこで培われた技術が民生品に応用され、新たなイノベーションを生み出す。この好循環を創り出すことこそ、政治の役割だ。横須賀がそのモデルケースとなることは、地方創生と国防強化を両立させる試金石となるだろう。
言葉で終わらせるな。問われるのは「国家の覚悟」
しかし、我々は手放しで賞賛するわけにはいかない。保守派として、言葉の先に具体的な行動と覚悟を求める。
第一に、安定的な防衛財源の確保である。防衛力の抜本的強化には、継続的かつ安定的な予算が不可欠だ。その場しのぎの増税論や国債頼みではなく、国家百年の計として、歳出改革を含む抜本的な財源確保策をどう描くのか。小泉氏を含む政治家には、国民に耳の痛い真実を語り、その道筋を示す責任がある。
第二に、国内の守りの徹底である。最新鋭の防衛技術が集積する拠点が生まれるのであれば、その技術を狙う諸外国の諜報活動も激化する。技術流出は、日本の安全保障を根底から揺るがす致命傷となりかねない。スパイ防止法の制定をはじめとする法整備を急ぎ、国内の「見えざる敵」から国家の機密を守り抜く体制を構築することが急務だ。
第三に、現場で国を護る自衛隊員への敬意と処遇改善である。「防衛の街」の主役は、日夜、厳しい任務に就く自衛隊員に他ならない。彼らが誇りを持って任務を全うできるよう、その処遇を抜本的に改善し、社会全体で敬意を払う文化を醸成することこそが、真の国防力強化に繋がる。政治は、その先頭に立たねばならない。
小泉氏の発言は、日本の国防意識を正常化させるための重要な一石である。だが、それはあくまで始まりに過ぎない。この言葉を、単なるスローガンや選挙向けのパフォーマンスで終わらせてはならない。
横須賀が「防衛の街」としての使命を全うするとき、それは日本が現実を直視し、自らの国を自らの手で守るという「国家の覚悟」を固めた証となるだろう。我々国民もまた、その覚悟を共有し、力強い国家の再建に向けて、政治家たちを後押しし、そして厳しく監視していく責務がある。
————-
ソース