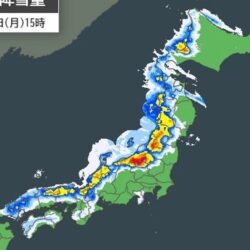【異例の人事】岸田政権、維新・遠藤敬氏の首相補佐官起用ー保守連携への一石か、それとも政局の具か
岸田文雄首相が、日本維新の会の遠藤敬国会対策委員長を首相補佐官に起用する方針を固めたとの報に、永田町に衝撃が走っている。野党の国会議員を、政権の中枢である首相補佐官に登用するという、まさに異例中の異例の人事だ。この一手を、我々保守派はどう捉えるべきか。単なる政局的な奇策と切り捨てるべきか、それとも大局を見据えた布石と見るべきか。冷静に検証したい。
評価すべき点:憲法改正への「本気度」の表れか
まず、この人事を前向きに評価するならば、それは岸田政権が「憲法改正」という国家の重要課題に対し、本腰を入れ始めた証と見ることができる。
ご存知の通り、日本維新の会は、自民党以上に憲法改正に前向きな姿勢を示してきた政党である。特に、安全保障環境が厳しさを増す中で、自衛隊の明記をはじめとする9条改正は、国家の存立に関わる喫緊の課題だ。しかし、自民党内ですら、いわゆる「ハト派」勢力の抵抗や、連立を組む公明党への配慮から、議論は常に停滞してきた。
ここに、改憲の強力な推進力を持つ維新から、国対の要である遠藤氏を迎え入れる。これは、改憲論議を加速させるための起爆剤となりうる。自民、維新、そして国民民主党などを巻き込んだ「改憲勢力」の結集を図り、具体的な発議へと駒を進めるための、極めて大胆な一手と評価できよう。遠藤氏は国対委員長として、他党との交渉に長けた実務家である。その実行力に期待する声があるのは事実だ。
また、安全保障や経済政策において、維新は野党第一党である立憲民主党などとは一線を画し、現実的な路線を歩んできた。いわゆる「批判ばかりの野党」とは異なり、是々非々で政策論議に応じる姿勢は、責任政党としての気概を感じさせる。こうした「話のできる」保守系野党と連携し、国益に適う政策を迅速に進めようとするならば、それは国政の安定に資するものであり、歓迎すべき動きと言える。
懸念すべき点:理念なき野合と政権浮揚策の危うさ
しかし、手放しでこの人事を礼賛することはできない。我々が最も警戒すべきは、この動きが国家観や理念を共有した上での連携ではなく、単なる「政局的な取引」に過ぎない可能性である。
支持率の低迷に喘ぐ岸田政権が、国会運営を円滑に進め、重要法案を通過させるため、維新の力を借りようとしているのではないか。つまり、政権浮揚のため、そして来たる解散総選挙を有利に進めるための「道具」として、維新を利用しようとしているという見方だ。もしそうであれば、これは国家の将来を見据えたものではなく、目先の政権維持を目的とした、極めて場当たり的な対応と言わざるを得ない。
また、維新の側にも思惑があるだろう。彼らの最終目標は、自民党に取って代わることにある。政権の中枢に食い込むことで存在感を示し、与党としての経験を積む。そして、いずれは自民党を内側から切り崩し、政権交代の足がかりにしようという戦略も透けて見える。今日の友は明日の敵、という永田町の鉄則を忘れてはならない。安易な連携は、将来的に自民党、ひいては保守本流の足元を揺るがす「トロイの木馬」を招き入れることになりかねない。
さらに、長年連立を組んできた公明党との関係はどうなるのか。改憲や安全保障政策において、維新と公明党の立ち位置は大きく異なる。この人事が、連立与党内に新たな亀裂を生む火種となる危険性も否定できない。政権の基盤をかえって不安定にさせる、諸刃の剣となる可能性も考慮すべきだ。
結論:結果で真価を問え
結論として、今回の遠藤氏の首相補佐官起用は、日本の将来を左右する大きな賭けである。
これが、憲法改正という歴史的事業を成し遂げるための「保守大連携」への第一歩となるのか。それとも、低迷する政権が延命を図るための、理念なき「野合」に終わるのか。その真価は、今後の具体的な政策推進、特に改憲論議が実際に前進するか否かにかかっている。
我々保守派は、期待と警戒の念をない交ぜにしながら、この異例の人事がもたらす今後の政局を注視していく必要がある。ただの政局の駒として終わらせるのではなく、真に国益に適う結果を生み出すことができるのか。岸田首相と、そして遠藤氏の覚悟と手腕が、今まさに問われている。
————-
ソース