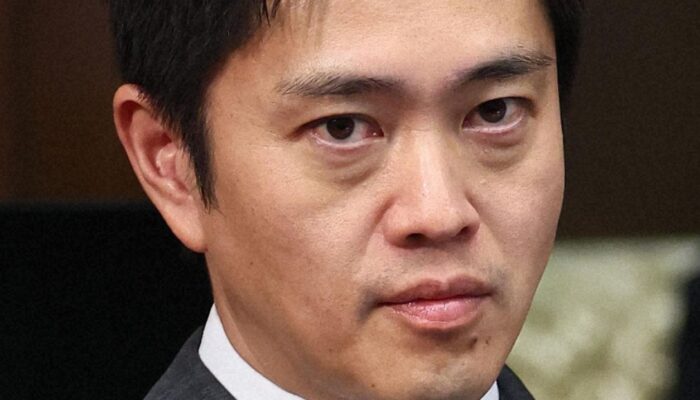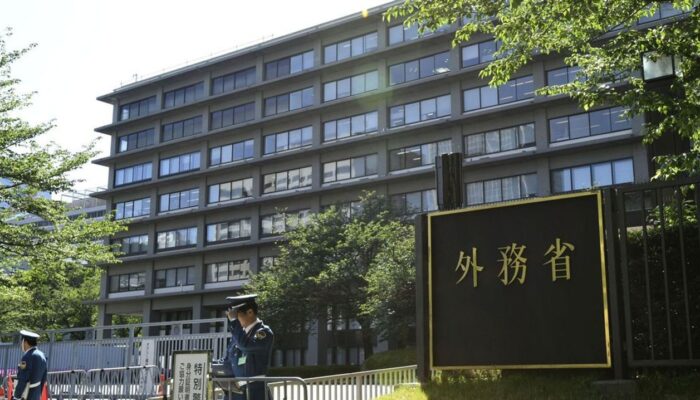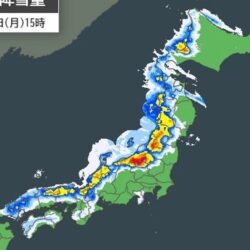自公連立、崩壊の序曲か?公明党の小選挙区撤退が示す「国益」の軽視
本日報じられた、公明党が次期衆院選において、自民党との候補者調整を行ってきた小選挙区の一部から候補者擁立を撤回する検討に入ったというニュースは、単なる一政党の選挙戦略の変更に留まらない。これは、長年にわたり日本の政治の安定を支えてきた自公連立政権の基盤を揺るがしかねない、極めて憂慮すべき事態である。我々保守派は、この動きを国家の安定という大局的な観点から厳しく検証せねばならない。
政権の安定を人質に取る自己中心的な戦術
今回の公明党の動きは、東京における選挙協力を巡る自民党との対立が引き金とされている。自民党の支援が見込めない埼玉14区や愛知16区などで「負け戦」を避けるという判断は、一見すると政党として合理的な判断のように映るかもしれない。
しかし、その本質は、自らの要求を通すために「連立離脱」をもちらつかせ、政権の安定そのものを人質に取る、極めて自己中心的かつ危険な戦術と言わざるを得ない。国家が内外に多くの課題を抱えるこの時期に、政権与党の一角が目先の選挙区の損得勘定で政権基盤を揺るがす行為は、国益を著しく損なうものだ。
「平和と福祉の党」を標榜するならば、まず優先すべきは政治の安定による国民生活の安寧ではないのか。今回の動きは、党の理念よりも組織防衛と議席の維持という党利党略を優先していると断じられても仕方あるまい。
「漁夫の利」を得るのは誰か
自公の選挙協力体制が崩壊すれば、誰が喜ぶのか。それは明白だ。脆弱な政策とイデオロギー闘争に明け暮れる立憲民主党や日本維新の会といった野党勢力である。
小選挙区制度において、与党が候補者を一本化できずに票が割れれば、野党候補が「漁夫の利」を得ることは火を見るより明らかだ。公明党の今回の決断は、結果的に日本の政治を混乱させ、安全保障や経済政策において現実離れした主張を繰り返す勢力を利することに繋がりかねない。
中国の軍事的脅威、北朝鮮の核・ミサイル開発、そしていまだデフレから完全脱却できない日本経済。こうした国難ともいえる課題に立ち向かうべき時に、与党内の内輪もめで貴重な政治的エネルギーを浪費し、国力を削ぐ愚を犯してはならない。公明党は、自らの行動がどのような結果を招くのか、その政治的責任を深く自覚すべきである。
自民党の驕りと指導力不足も問われる
もちろん、この事態を招いた責任の一端は自民党にもある。長年の連立関係にあぐらをかき、公明党の協力を「当然のもの」と考える驕りはなかったか。特に、今回の火種となった東京での選挙協力を巡る対応には、脇の甘さがあったと言わざるを得ない。連立パートナーに対する敬意と丁寧な調整を欠いたことが、今日の深刻な亀裂を生んだのだ。
これは、岸田政権の指導力不足の表れでもある。政権運営の要である与党内の意思疎通と信頼関係を維持・強化することは、総理総裁の最も重要な責務の一つだ。この基本的なマネジメントが機能不全に陥っているとすれば、今後の政権運営そのものに大きな不安が残る。
大局に立ち返り、連立関係の再構築を
もはや、単なる選挙区調整の問題ではない。自公両党は、目先の感情的な対立や党利党略を捨て、日本の政治の安定と国益という大局に立ち返らねばならない。
公明党は、政権与党として、その一挙手一投足が国家の将来に与える影響の大きさを再認識し、責任ある行動を取るべきだ。そして自民党は、連立パートナーへの配慮を怠ったことを猛省し、真摯な対話を通じて信頼関係を再構築する努力を尽くさなければならない。
このまま両党の亀裂が深まれば、それは日本の政治の不安定化、ひいては国力の低下に直結する。我々保守層は、政権の安定を強く望む国民の一人として、両党がこの危機を乗り越え、国益に適う賢明な判断を下すことを強く注視していく。
————-
ソース