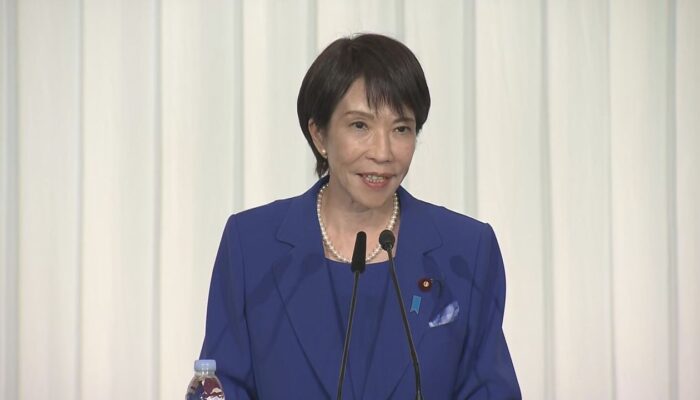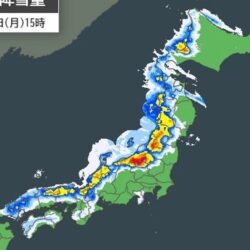行き過ぎた「文化の盗用」批判は、文化交流を殺す
先日、日本でネパール人が被る伝統的な帽子をファッションとして着用した人が、インターネット上で批判を浴び、戸惑っているというニュースが報じられた。この種の騒動は、昨今「文化の盗用(Cultural Appropriation)」という言葉と共に、後を絶たない。
一見すると、他国文化への配慮を求める正当な主張に見えるかもしれない。しかし、我々はこの風潮に潜む危うさに、もっと敏感になるべきではないだろうか。結論から言えば、このような過剰な批判は、文化への敬意とは似て非なるものであり、むしろ文化交流を萎縮させ、社会に分断をもたらす危険な思想である。
文化への敬意と「盗用」批判は全くの別物
まず大前提として、他国の文化や伝統に敬意を払うことは、人として当然の心得である。神聖なシンボルを冒涜したり、特定の民族を嘲笑する目的でその文化を利用したりすることは、断じて許されるべきではない。これは、自国の歴史や伝統を重んじる我々保守派にとっても、至極当然の価値観である。
しかし、今回のネパール帽の件は、そうした悪意のある事例とは明らかに異なる。報道によれば、着用者は純粋にそのデザインに魅了され、ファッションの一部として取り入れていただけだという。そこには、ネパール文化を貶める意図など微塵も感じられない。にもかかわらず、「文化の盗用だ」と糾弾することは、あまりにも短絡的で、言葉の暴力に等しい。
文化は誰かの「所有物」ではない
そもそも「文化の盗用」という概念自体が、極めて偏狭な文化観に基づいている。文化とは、本来、異なる文化圏が出会い、影響を与え合い、混じり合う中で豊かになっていくものである。
我が国、日本の歴史を振り返れば、その事実は火を見るより明らかだ。漢字、仏教、儒教は大陸から伝来し、我々の精神文化の根幹を成した。スーツを身に着け、パンを食し、クリスマスを祝う。これら全てを「文化の盗用」と断罪する者がいるだろうか。海外の優れた文化を敬意をもって取り入れ、それを日本独自の形に昇華させてきた「和魂洋才」の精神こそ、日本の文化を豊かにしてきた原動力ではなかったか。
「文化の盗用」という批判は、文化をあたかも特定の集団だけが独占できる「所有物」であるかのように扱う。これは、文化の持つ本来の流動性や発展性を否定する、非常に硬直的で不毛な考え方だ。異文化への憧れや好奇心という、人間にとって最も自然な感情に「盗用」という罪のレッテルを貼り、人々が異文化に触れる機会を奪い、世界を分断へと向かわせる。
行き過ぎたポリコレがもたらす不寛容な社会
この問題の根底には、欧米から輸入された行き過ぎたポリティカル・コレクトネス(ポリコレ)の思想がある。彼らは、あらゆる事象を「差別」や「搾取」の構造に当てはめて解釈し、悪意のない個人を断罪することで、自らの正義を誇示しようとする。
しかし、その結果もたらされるのは、互いの顔色を窺い、些細な言動に怯えなければならない、不寛容で息苦しい社会である。ファッションを自由に楽しむことさえ、誰かを傷つけるかもしれないと自己検閲を強いられる。このような社会が、果たして健全と言えるだろうか。
本当に守るべきは、異文化に対する健全な好奇心と、敬意に基づいた自由な交流である。ネパール帽の美しさに惹かれたのなら、それをきっかけにネパールの歴史や文化を学ぶことこそ、真の国際理解への第一歩となるはずだ。
表面的な記号だけを捉えて他者を攻撃する「ポリコレ狩り」のような風潮に、我々は断固として異を唱えなければならない。大切なのは、着用を禁止することではなく、その背景にある文化への敬意を育むことだ。文化交流の道を閉ざすのではなく、むしろ押し広げることこそ、我々が目指すべき社会の姿である。
————-
ソース